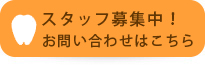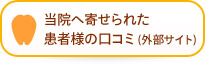生活習慣病〈糖尿病〉
2023年10月30日
皆さんこんにちは、淀川区加島の川越歯科医院です。
今回は生活習慣病の中の1つ糖尿病についてのお話をしていきます。
*糖尿病とは
・食事をすると基本的には血糖値が上がります。
しかし、すい臓から出るホルモンの「インスリン」によって血糖値を一定の数値に保つことができます。
逆に言えば「インスリン」が上手く機能していなければ血糖値を下げることができずに糖尿病になってしまいます。
初期症状としては「喉がやたらと渇く」「排尿の回数が増える」「疲れやすくなる」などです。
・インスリンとはすい臓の中にはランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集まりがありさらにその中のベータ細胞から分泌されるホルモンです。
ちなみに人間の体の中で血糖値を下げることができるホルモンはインスリンだけです。
*血糖値について
・血糖値とは血液中のブドウ糖の量のことになります。
・空腹値血糖値
10時間以上水以外飲まずに絶食し検査したときにわかる血糖値です。
正常型…100未満
境界型…110~126未満
糖尿病型…126以上
となっており、126以上血糖値があると糖尿病と診断されます。
この数値だと糖尿病のリスクが高くなっていることがわかります。
※境界型とは血糖値が正常型と糖尿病の間にある数値です。
・随時血糖値
食事の時間に関わらずに検査したときにわかる血糖値です。
正常型…140未満
境界型…141~200未満
糖尿病型…200以上
となっており200以上だと糖尿病と診断されます。
・ヘモグロビンA1c(以下HbA1c)
HbA1cは過去1~2ヵ月の血糖値の平均の数値です。
年齢でも正常値は変わりますので注意が必要です。
正常型…5.2未満
境界型…5.2~6.1未満
糖尿病型…6.1以上
となっており6.1以上だと糖尿病と診断されます。
*1型糖尿病
・1型糖尿病は正確には生活習慣病ではありません。
何らかの理由ですい臓のベータ細胞が破壊されインスリンが上手く分泌できなくなり、結果血糖値を下げられなくなる糖尿病です。
10~20代に多く若年性糖尿病とも言われます。
*2型糖尿病
・2型糖尿病は普段の生活の乱れや遺伝的なもので引き起こされる糖尿病です。
高血糖になるものを常時食べているとその分すい臓の負担も大きくなり、インスリンの分泌が少なくなったり、効き目が弱くなったりします。
運動不足や過食等が原因ですので規則正しい生活を送ることが予防のために重要です。
*糖尿病の3大合併症
・糖尿病網膜症
高血糖の状態が続くと網膜内の毛細血管がつまり視力低下や失明してしまいます。
・糖尿病腎症
血液をろ過し尿を作る腎臓の毛細血管がつまりろ過機能が正常に働かなくなってしまいます。
最悪人工透析を行う必要も出てきます。
・糖尿病神経障害症
全身にある毛細血管への血流がつまったり悪くなったりすると神経細胞への血液供給が途絶えてしまいます。
そうなると手足の痛みや痺れ、最悪切断しなくてはならないという症例もある症状です。
*歯周病との関連
・歯周ポケットから血管に炎症関連の化学物質が流れてしまうとインスリンが効きにくくなり糖尿病が悪化してしまいます。
歯周病を治療すると血糖値が改善される例も多く報告されています。
逆に糖尿病を治療すると歯周病が改善されるということもあります。
正しい生活習慣で糖尿病を予防していきましょう!
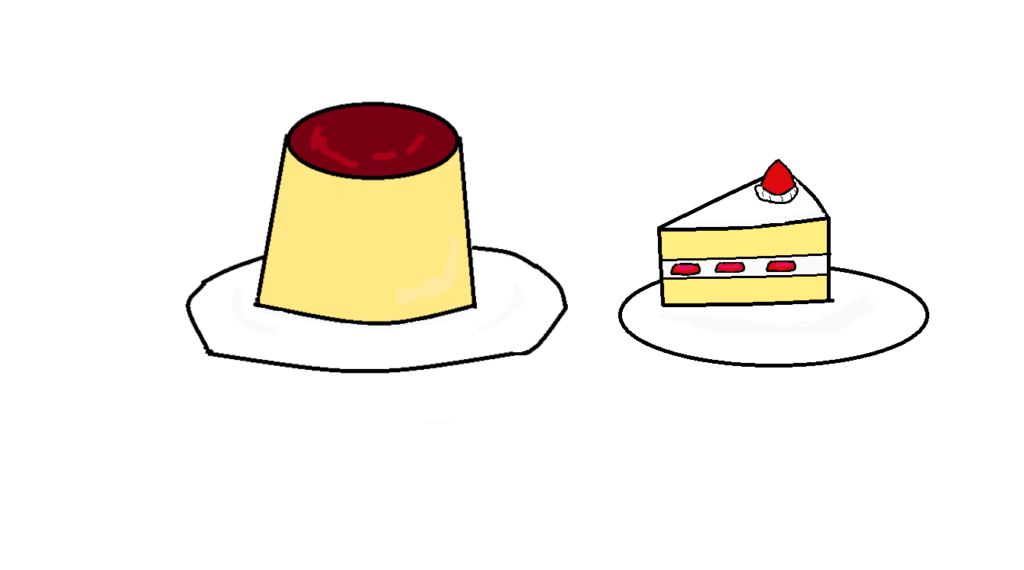

 「加島」駅から徒歩で
「加島」駅から徒歩で 「十三」駅からバスで
「十三」駅からバスで 「尼崎」駅から電車で
「尼崎」駅から電車で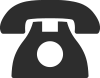 06-6302-2423
06-6302-2423