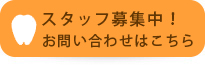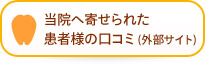アルコールの摂りすぎに注意!
2023年09月25日
皆さんこんにちは、淀川区加島の川越歯科医院です。
突然ですが皆さんお酒は好きですか?
〈酒は百薬の長〉という言葉にもあるように適切に飲むことができればメリットを得られます。
ですが逆に適正量を超えて摂取してしまうとお口の中は勿論、身体全体にも悪影響を与えてしまいます。
今回は薬にも毒にもなってしまうお酒のことについてお話していきます!
*お酒を適量飲むメリット
・食欲増進
適量のお酒であれば胃酸の分泌が促進され食欲が増し必要な栄養を摂取しやすいです。
・リラックス効果、ストレス解消
アルコールは理性を司る大脳新皮質(脳の表層部分)の働きを鈍くさせることで心の緊張をほぐしリラックス効果やストレス解消にも役立つことがあります。
・円滑なコミュニケーション
お酒を適量飲むことで精神が高揚し会話が弾みやすくなりとされています。
お酒にはメリットが色々あります。
ただ再度知っていて欲しいのはあくまでも適量のお酒を飲んだ時ということです。
*お酒の適量
・性別や年齢などで個人差はありますが1日純アルコール20g程とされています。
・純アルコール20gに相当するお酒の量の例
ビール(5%) 500ml缶 1本
ワイン 200ml 約グラス2杯弱
ウイスキー 60ml 約ダブル1杯
とされています。
適量に気を付けお酒は楽しく嗜みましょう。
最初に記した通り、お酒は適量であればメリットを得られることが多いです。
逆にアルコールを適量以上摂取してしまうとどうなるでしょうか
*お酒の虫歯リスク
・糖分の入ったお酒
アルコール自体に糖分は含まれていませんが種類によっては糖分が入っているので虫歯のリスクが高くなってしまいます。
糖分が含まれるのは基本的に醸造酒になっています。
醸造酒…ワイン、ビール、日本酒など
逆に蒸留酒にはほとんど糖が含まれていません。
蒸留酒…ウイスキー、焼酎、ブランデーなど
糖が含まれていない分虫歯のリスクは減りますが飲みすぎには注意が必要です。
・Ph(ペーハー)が低い
Phとは酸性、中性、アルカリ性を示す単位です。
数字が低ければ低い程酸性になります。
口腔内は個人差などありますがPh5.4以下になるとエナメル質が溶け出してしまいます。
糖分がほとんど含まれないウイスキーでもPh5.0程などでお酒は虫歯のリスクになることがわかります。
・利尿作用、脱水作用
アルコールには利尿作用があり、さらにアルコールを分解すること自体にも体の水分が必要です。
摂取したお酒以上の水分が失われてしまうので口腔内が乾燥し虫歯・歯周病のリスクが上がり最悪脱水症状を引き起こすこともあります。
・歯磨きが億劫になってしまう
お酒を飲むと、いい気分になれますよね。
ただそれと同時に歯磨きが億劫に感じて歯磨きがキチンとできず、磨き残しが多くなることがあります。
お酒以外もそうですが、食べたり飲んだりした後は歯磨きをしっかり行いましょう!
お酒にもメリット、デメリットがあります。
お口の中や全身の健康状態を考えて楽しくお酒を飲みましょう
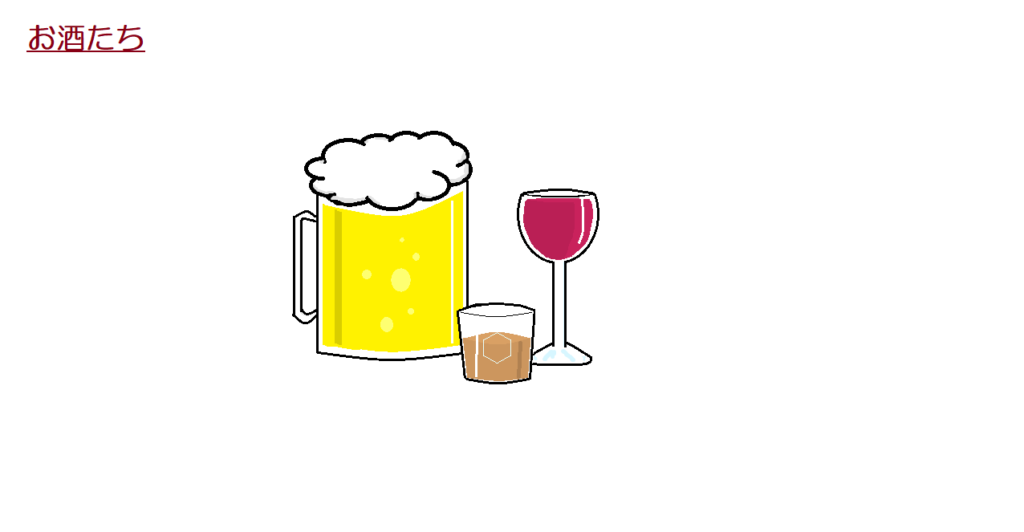

 「加島」駅から徒歩で
「加島」駅から徒歩で 「十三」駅からバスで
「十三」駅からバスで 「尼崎」駅から電車で
「尼崎」駅から電車で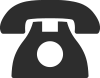 06-6302-2423
06-6302-2423